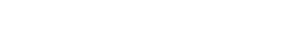| 氏名 | 帖佐 尚人 |
|---|
| 研究業績等に関する事項(※原則として直近5年間の業績を表示) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 著書,学術論文等の名称 | 単著, 共著の別 |
発行又は 発表の年月 |
発行所,発表雑誌等 又は発表学会等の名称 |
||||
| 著書 | |||||||
| 1.ワークで学ぶ道徳教育 | 共著 | 平成28年2月 | ナカニシヤ出版 | ||||
| 2.ワークで学ぶ教職概論 | 共著 | 平成29年4月 | ナカニシヤ出版 | ||||
| 3.幼児・初等教育入門 | 共著 | 平成30年2月 | ラグーナ出版 | ||||
| 4.ワークで学ぶ学校カウンセリング | 共著 | 令和元年7月 | ナカニシヤ出版 | ||||
| 5.ワークで学ぶ道徳教育 増補改訂版 | 共著 | 令和2年3月 | ナカニシヤ出版 | ||||
| 6.新薩摩学14 人口減少社会・鹿児島の教育のゆくえ | 共著 | 令和2年3月 | 南方新社 | ||||
| 7.幼児・初等教育入門Ⅱ | 共著 | 令和3年8月 | ラグーナ出版 | ||||
| 8.現代アメリカ教育ハンドブック 第2版 | 共著 | 令和3年11月 | 東信堂 | ||||
| 学術論文 | |||||||
| 1.子どもに対する教育的介入の正当化に関する一考察:今日的なパターナリズムを巡る議論をもとに | 単著 | 平成21年3月 |
早稲田大学教育学会紀要 第10号 |
||||
| 2.子どもに対するパターナリズムの正当化についての一考察:1970年代の英米におけるその初期の議論の検討を中心に(査読付) | 単著 | 平成21年9月 |
早稲田大学大学院教育学研究科紀要.別冊 第17-1号 |
||||
| 3.S.E.ノルデンボの「子どもに対するパターナリズム」論(査読付) | 単著 | 平成22年3月 |
早稲田大学大学院教育学研究科紀要.別冊 第17-2号 |
||||
| 4.子どもに対するパターナリズムについての理論的研究: 自律を尊重する教育的介入論の構築を企図して | 単著 | 平成22年3月 | 早稲田大学大学院教育学研究科修士論文 | ||||
| 5.我が国における子どもの権利論の特徴と問題点:「親の教育権」論との関連から | 単著 | 平成22年3月 |
早稲田大学教育学会紀要 第11号 |
||||
| 6.子どもの権利論の意義とその問題点に関する一考察:子どもの権利制約原理としてのパターナリズムの射程(査読付) | 単著 | 平成22年9月 |
早稲田大学大学院教育学研究科紀要.別冊 第18-1号 |
||||
| 7.我が国における児童虐待問題と生徒指導上の課題:学校の虐待予防・防止機能に焦点を当てて | 単著 | 平成23年3月 |
早稲田大学教育学会紀要 第12号 |
||||
| 8.H.ラフォレットの「親のライセンス化」論:児童虐待と親の教育権規制を巡る一議論として(査読付) | 単著 | 平成23年9月 |
早稲田大学大学院教育学研究科紀要.別冊 第19-1号 |
||||
| 9.戦後我が国における子どもの問題行動等に対する一次予防教育:中学校段階におけるその取り組みの歴史的展開と今後の展望 | 単著 | 平成24年3月 | 早稲田大学教育総合研究所2011年度一般研究部会『子どもの問題行動防止と健全化育成をめぐる総合的対策の研究報告書:学校内の改善および学校外関係機関とくに警察との連携を中心に』 | ||||
| 10.児童虐待予防と特別活動:とりわけ学校健康診断に着目して | 単著 | 平成24年3月 |
早稲田大学教育学会紀要 第13号 |
||||
| 11.札幌市における子どもの問題に対する多機関連携制度:学校を端緒とした取組に着目して(査読付) | 共著 | 平成24年3月 |
早稲田大学大学院教職研究科紀要 第4号 |
||||
| 12.北九州市及び札幌市立小・中学校の生徒指導に関する質問紙調査結果(報告):生徒指導体制と予防教育に焦点を当てて | 共著 | 平成24年3月 |
早稲田大学社会安全政策研究所紀要 第4号 |
||||
| 13.子どもの自由制約原理としてのパターナリズム:その諸正当化モデルの検討(査読付) | 単著 | 平成24年5月 |
教育哲学研究 第105号 |
||||
| 14.チャイルド・パターナリズム正当化を巡る補完的諸考察:D.パーフィットの人格同一性論と「大人‐子ども区分」の正当化 | 単著 | 平成25年3月 |
学術研究(早稲田大学) 第61号 |
||||
| 15.学校保健ベースの教育相談と健康教育:その現状と展望に関する日米比較 | 単著 | 平成25年3月 |
早稲田大学教育学会紀要 第14号 |
||||
| 16.J.ウェストマンの親ライセンス制度構想:1990年代における「親のライセンス化」論の展開として | 単著 |
平成25年7月 |
鹿児島国際大学福祉社会学部論集 第32-1号 |
||||
| 17.生涯を通じたキャリアとしてのペアレントフッド:J.ウェストマンの親論と児童虐待予防理論の分析から(査読付) | 単著 | 平成25年9月 |
早稲田大学大学院教育学研究科紀要.別冊 第21-1号 |
||||
| 18.アメリカにおける学校拠点型保健センター(SBHC):その発展と現在(査読付) | 単著 | 平成25年12月 |
アメリカ教育学会紀要 第24号 |
||||
| 19.カリフォルニア州学校保健センター連盟の学校保健施策:その学校拠点型保健センター(SBHC)支援と健康教育プログラム実践の分析 | 共著 | 平成26年1月 |
鹿児島国際大学福祉社会学部論集 第32-3号 |
||||
| 20.「親のライセンス化」の代替策の検討(1):H.ラフォレットの理論変遷の分析から | 単著 | 平成26年7月 |
鹿児島国際大学福祉社会学部論集 第33-1号 |
||||
| 21.「親のライセンス化」の代替策の検討(2):J.ウェストマンの青年期妊娠・出産規制論 | 単著 | 平成26年10月 |
鹿児島国際大学福祉社会学部論集 第33-2号 |
||||
| 22.アメリカにおける学校拠点型保健センター(SBHC)の実際 : カリフォルニア州アラメダ郡を事例として | 共著 | 平成27年3月 |
鹿児島国際大学福祉社会学部論集 第33-4号 |
||||
| 23.戦後我が国における親の教育権論の展開 | 単著 | 平成28年2月 |
鹿児島国際大学福祉社会学部論集 第34-4号 |
||||
| 24.キャラクター・エデュケーションと性教育:アメリカにおける自己責任教育プログラム(PREP)についての一考察 | 単著 | 平成29年7月 |
鹿児島国際大学福祉社会学部論集 第36-1号 |
||||
| 25.日本の学校保健と倫理:学校におけるヘルスプロモーション推進についての倫理学的考察 | 単著 | 平成29年10月 | 科学研究費補助金基盤研究B最終報告書『EU諸国等における学校基盤の包括的健康教育の研究:地域と協働する学校』 | ||||
| 26.特別活動における主体的・対話的な深い学びのための指導方法と評価に関する研究:「創造的な学び」による学級活動指導案の開発 | 共著 | 平成30年2月 |
鹿児島国際大学福祉社会学部論集 第36-4号 |
||||
| 27.カリフォルニア州アラメダ郡における学校-SBHC間連携:サービス調整チーム(COST)に基づく児童生徒支援システムの分析(査読付) | 単著 | 平成30年3月 |
アメリカ教育学会紀要 第28号 |
||||
| 28.完全義務/不完全義務区分からみた我が国の道徳教育の特徴と問題点:教科道徳の指導内容充実に向けた基礎的研究として(査読付) | 単著 | 平成31年3月 |
倫理道徳教育研究 第2号 |
||||
| 29.コロナ禍を踏まえた米国の学校保健の動向:学校拠点型保健センター(SBHC)による児童生徒支援及び行動改善を中心に | 単著 | 令和3年8月 | 国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター『「社会情緒的(非認知)能力の発達と環境に関する研究:教育と学校改善への活用可能性の視点から」中間報告書』 | ||||
| 30.コロナ禍におけるインティマシー(親密さ)の変容とその教育的含意:子どもへのワクチン接種義務化の議論にも絡めて(査読付) | 単著 | 令和3年11月 |
教育哲学研究 第124号 |
||||
| 31.教科としての保健学習と「社会性と情動の学習」の接続(1):アメリカにおける議論の動向 | 単著 | 令和5年12月 | 鹿児島国際大学福祉社会学部論集第42-3号 | ||||
| 32.教科としての保健学習と「社会性と情動の学習」の接続(2):授業構想例の分析と日本への示唆 | 単著 | 令和6年2月 | 鹿児島国際大学福祉社会学部論集第42-4号 | ||||
| 33.米国の保健学習における「社会性と感情の学習」と学校拠点型保健センター(SBHC)による児童生徒支援及び行動改善 | 単著 | 令和6年3月 | 国立教育政策研究所『「社会情緒的(非認知)能力の発達と環境に関する研究:教育と学校改善への活用可能性の視点から」(学校改善チーム)最終報告書』 | ||||
| 34.カリフォルニア州における学校風土調査の活用の実際 | 共著 | 令和6年3月 | 国立教育政策研究所『「社会情緒的(非認知)能力の発達と環境に関する研究:教育と学校改善への活用可能性の視点から」(学校改善チーム)最終報告書』 | ||||
| 公的研究等への関与 | |||||||
| 1.子どもを犯罪から守るための多機関連携モデルの提唱 | 共同 | 平成21年10月~平成24年3月 |
独立行政法人科学技術振興機構(JST)社会技術研究開発センター(RISTEX)研究開発プロジェクト ※研究補助者として関与 |
||||
| 2.子どもの問題行動防止と健全化育成をめぐる総合的対策の研究:学校内の改善および学校外関係機関とくに警察との連携を中心に | 共同 | 平成23年4月~平成24年3月 |
早稲田大学教育総合研究所2011年度一般研究部会 ※研究協力員として関与 |
||||
| 3.子どもの非行・虐待防止のための地域社会ネットワークの実証的研究 | 共同 | 平成24年4月~平成27年3月 |
科学研究費助成事業基盤研究(C) ※連携研究者として関与 |
||||
| 4.チャイルド・パターナリズム正当化論の体系化に向けた基礎的研究 | 単独 | 平成24年4月~平成25年3月 |
早稲田大学2012年度特定課題研究助成費(新任の教員等) ※研究代表者として実施 |
||||
| 5.アメリカにおける学校拠点型保健センター(SBHC)とその我が国への導入可能性 | 単独 | 平成25年4月~平成28年3月 |
科学研究費助成事業若手研究(B) ※研究代表者として実施 |
||||
| 6.EU諸国等における学校基盤の包括的健康教育カリキュラムの研究―地域と協働する学校 | 共同 | 平成28年4月~平成30年3月 |
科学研究費助成事業基盤研究(B) ※連携研究者として関与 |
||||
| 7.重大非行事案防止のための多機関連携による非行少年等とその家庭への支援に関する研究 | 共同 |
平成29年4月 ~令和2年3月 |
科学研究費助成事業基盤研究(C) ※連携研究者として関与 |
||||
| 8.社会情緒的(非認知)能力の発達と環境に関する調査研究:教育と学校改善への活用可能性の視点から | 共同 |
令和2年4月 ~令和5年3月 |
国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センタープロジェクト研究 ※研究分担者として関与 |
||||
| 9.不登校・いじめ等の生徒指導上の諸課題の現状と学校を基盤とした効果的な取組等に関する包括的な学校風土研究:地域との連携協定に基づく中・長期的な生徒指導重点事業 | 共同 | 令和6年4月~令和10年3月(予定) |
国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センタープロジェクト研究 ※研究分担者として関与 |
||||
| 学会発表等 | |||||||
| 1.子どもに対する教育的介入の正当化に関する一考察:今日的なパターナリズムを巡る議論をもとに | 単独 | 平成21年3月 | 早稲田大学教育学会第10回大会(於・早稲田大学) | ||||
| 2.子どもに対するパターナリズムの正当化問題:S.E.ノルデンボの議論の分析・検討をもとに | 単独 | 平成21年10月 | 教育哲学会第52回大会(於・名古屋大学) | ||||
| 3.我が国における子どもの権利論の特徴と問題点:「親の教育権」論との関連から | 単独 | 平成22年3月 | 早稲田大学教育学会第11回大会(於・早稲田大学) | ||||
| 4.アメリカにおける児童虐待問題とその事前規制理論:主としてH.ラフォレットの「親のライセンス化」論の検討から | 単独 | 平成22年8月 | 日本教育学会第69回大会(於・広島大学) | ||||
| 5.チャイルド・パターナリズム正当化に関する基礎的考察:「将来的自己への侵害」モデルの理論的基盤としての人格同一性論の検討 | 単独 | 平成22年10月 | 教育哲学会第53回大会(於・中央大学) | ||||
| 6.我が国における児童虐待問題と生徒指導上の課題:学校の虐待予防・防止機能に焦点を当てて | 単独 | 平成23年3月 | 早稲田大学教育学会第12回大会(於・早稲田大学) | ||||
| 7.「大人‐子ども区分」の正当化に関する一考察:チャイルド・パターナリズム論の一展開として | 単独 | 平成23年10月 | 教育哲学会第54回大会(於・上越教育大学) | ||||
| 8.児童虐待予防と特別活動:とりわけ学校健康診断に着目して | 単独 | 平成24年3月 | 早稲田大学教育学会第13回大会(於・早稲田大学) | ||||
|
9.J.ウェストマンの親思想に関する一考察:とりわけparenthood概念の分析から |
単独 | 平成24年9月 | 教育哲学会第55回大会(於・早稲田大学) | ||||
| 10.アメリカ学校保健施策の今日的展開:学校拠点型保健センター(SBHC)に着目して | 単独 | 平成24年10月 | アメリカ教育学会第24回大会(於・九州大学) | ||||
| 11.学校保健ベースの教育相談と健康教育:その現状と展望に関する日米比較 | 単独 | 平成25年3月 | 早稲田大学教育学会第14回大会(於・早稲田大学) | ||||
| 12.カリフォルニア州における「介入指導に対する反応」(RTI)モデルの一展開:「サービス調整チーム」(COST)に基づく児童生徒支援システムを中心に | 単独 | 平成26年10月 | アメリカ教育学会第26回大会(於・名古屋大学) | ||||
| 13.学校と学校拠点型保健センター(SBHC)との連携による児童生徒支援の現状と展望:カリフォルニア州アラメダ郡での聞き取り調査を踏まえて | 単独 | 平成27年10月 | アメリカ教育学会第27大会(於・武庫川女子大学) | ||||
| 14.公衆衛生倫理とパターナリズム:英語圏におけるその議論展開と道徳教育及び健康教育への視座 | 単独 | 平成28年8月 | 日本教育学会第75回大会(於・北海道大学) | ||||
| 15.完全義務/不完全義務区分からみた道徳の内容項目の問題点:教科道徳の指導内容充実のための一試論 | 単独 | 平成29年12月 | 日本倫理道徳教育学会第2回大会(於・筑波大学) | ||||
| 16.アメリカにおける学校拠点型保健センター(SBHC) | 単独 | 令和3年9月 | 「子どもみんなプロジェクト」講演会(オンライン) | ||||
| 17.学校拠点型保健センター(SBHC)による児童生徒の行動改善とコロナ禍における学校保健の動向 | 単独 | 令和3年10月 | アメリカ教育学会第33回大会(於・日本大学[オンライン]) | ||||